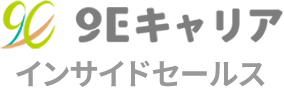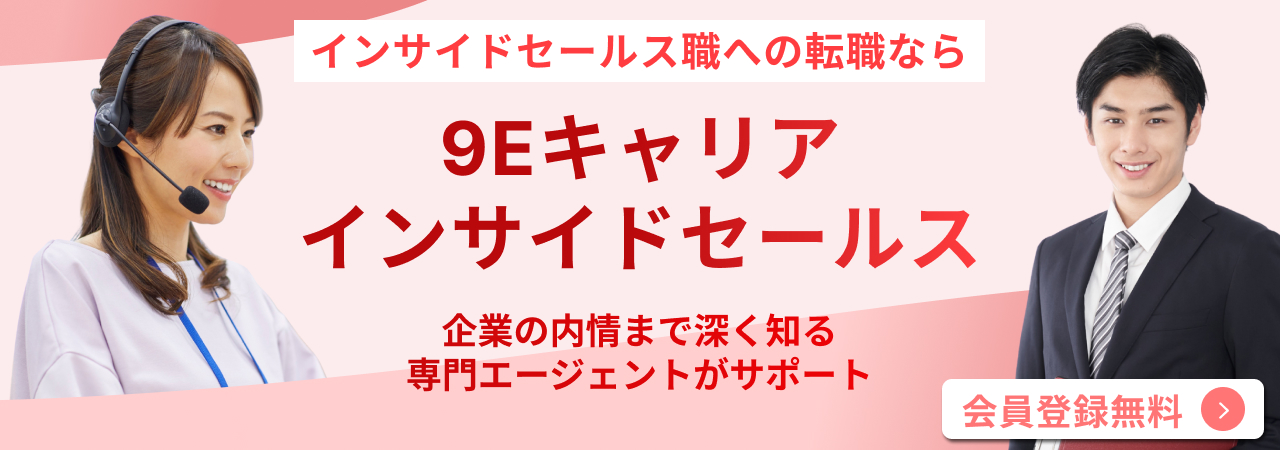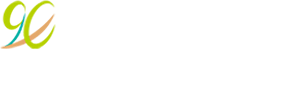2025年4月21日公開
最終更新日:2025年12月23日
インサイドセールスの役割とは? メリットや導入成功のポイントなど基礎知識を解説!
インサイドセールスの役割に注目が集まっています。インサイドセールスは営業プロセスのなかで内勤での営業活動を担う職種です。その主な役割はリードナーチャリングなどですが、それだけがインサイドセールスではありません。
この記事では、メリットや導入成功のポイントなども含め、インサイドセールスの役割を中心に導入や転職に役立つ基礎知識を解説します。
【関連記事】当社が運営する「インサイドセールス転職支援サービス」の特徴・選ばれる理由・登録のメリットについてご紹介。
インサイドセールスの役割
インサイドセールスは営業プロセスのなかで重要な役割を担っています。
非対面で営業活動を行う
インサイドセールスは、一般に営業職でイメージする客先を訪問するタイプの職種ではなく、内勤で職務を遂行する営業職です。直接的に顧客と顔を合わせるわけではない非対面、訪問なしの営業活動は、営業プロセスの効率化に役立っています。分業化された営業プロセスにおいては多くの場合、マーケティングの次のステップを担っており、後に続くフィールドセールスに引き継ぐまでが担当範囲です。
リードの育成プロセスを担う
インサイドセールスの一般的な役割としては、リードの育成(リードナーチャリング)がメインだといえます。接点がないか、あったとしても関係性の薄い顧客を担当し、中長期的な施策で信頼関係を構築することが重要な任務です。その過程で顧客の課題を把握し、ソリューションの提案を行うなど、フィールドセールスが商談をまとめることが可能なレベルになるまで見込み客として育てます。
インサイドセールスは営業職の一種ではあるものの、分業化した社内の営業プロセスにおける一般的な特徴として、自らクロージングを行うことはありません。クロージングはあくまでもフィールドセールスの役割です。
SDRとBDRという2つの役割

インサイドセールスにはアプローチのきっかけ、営業手法によってSDRとBDRの2種類の役割があります。
SDR(反響型営業)という役割
SDRはSales Development Representativeの略称であり、反響型営業を意味します。SDRでは自社の公式サイトやブログ、SNSなどのメディアやセミナー、広告などの接点を利用して資料のダウンロードや問い合わせをしてきた顧客がターゲットです。
顧客の側からアクセスしてきた時点で、少なくとも自社の商品やサービスの購入、利用を検討しているか、興味を持っていることがわかります。インサイドセールスとしては、顧客の気持ちが熱いうちに適切な対応を行い、一覧でリストに載っている顧客を少しでも多く有望な見込み客として育てることが重要です。アプローチに利用する手段には電話やメール、メルマガなどがあります。
SDRでは、製品や商材によっては、早期のクロージングにつながるケースが少なくありません。その場合、購入の意思決定の早さの関係もあり、大企業よりも中小企業が多く、大型案件よりも小型案件が多いといえます。
BDR(新規開拓型営業という役割)
BDRはBusiness Development Representativeの略で、新規開拓型営業のことです。SDRとは異なり、ターゲットのほうからアクセスしてくるわけではありません。インサイドセールスとして、自社の商品やサービスを売り込むのに相応しい企業を選んでアプローチします。
BDRのターゲティングでは、相手先が自社や自社の商品・サービスを認知しているか否かを問いません。しかし、認知しているか否かがハッキリしない相手に対しては、知られていないものとしてアプローチします。BDRのアプローチで主に使用される手段は、テレアポやDMです。
BDRはゼロから商談化することを目指す活動であり、中長期的な視点でじっくりと関係を構築します。そのため、大型案件が期待できる大企業に向けたインサイドセールスに適した活動です。
インサイドセールスの職務

インサイドセールスが担う役割を果たすための、具体的な職務、業務内容について解説します。
リードへのアプローチ
インサイドセールスの職務は一般にリードへのアプローチからはじまります。前述のSDRにおいては、アクセスしてきた顧客への対応で、自社として最初に接触するのがインサイドセールスです。BDRの場合は、テレアポやDMを打つ作業をインサイドセールスが行います。このように、インサイドセールスは営業プロセスのなかで、対顧客の初動となる職務を担うポジションであり、重要度が高い職種です。
リードナーチャリング
顧客との初回接触を行った後のインサイドセールスは、信頼関係の構築を行いながら見込み客(リード)としての確度を上げる、育てる(ナーチャリング)職務を行います。SDRにおいて、マーケティング部門から有望なリード(MQL)として引き継いだ場合には、成約の確率が高いリード(SQL)へのナーチャリングがインサイドセールスの職務です。
リードナーチャリングの手段としては、ヒアリングやソリューションの提案、フォローのための架電や問い合わせメールへの返信、ステップメールの作成と配信などがあります。また、顧客にとって有益なお役立ちコンテンツづくり、記事の執筆、ウェビナーの開催なども重要な職務です。
顧客の課題や要望を把握するために欠かせないヒアリングにおいては、BANT条件を意識する必要があります。BANT条件とは、予算(Budget)、権限・決裁権(Authority)、必要性(Need)、時間枠・導入時期(Time frame)の4要素を欠かせない条件としたものです。
適切なナーチャリングを可能とするためには、どれだけの予算が確保できるのか、決裁権を持っているのは誰か、ソリューションとしてのマッチング度合いによる必要性はどうか、導入はいつ頃になりそうかという4要素を客観的なデータとして聞き出す必要があります。
フィールドセールスに引き継ぐ
リードナーチャリングを行ったインサイドセールスは、クロージングに向けた商談が可能な時期・タイミングを見計らって、顧客をフィールドセールスに引き継ぎます。引継ぎが終わっても連携は続き、当該顧客に関するインサイドセールスの職務が終わるわけではありませんが、一つの大きな区切りであることは間違いありません。
各ポジションとの連携
インサイドセールスの職務には他の各ポジションとの連携が欠かせません。リードを引き受けるマーケティング、引き渡すフィールドセールスや成約後の顧客を担当するカスタマーサクセスなど、それぞれが営業プロセスを分担するチーム内の連携は大前提です。
インサイドセールスはリードの情報をダイレクトにキャッチするポジションであることから、自分の職務だけでなく他部門の仕事にとっても連携の重要性が大きいといえるでしょう。
また、営業プロセスの部門だけが会社の業績を左右するわけではないため、その他の各部門、担当者との円滑かつ密接な連携も重要な職務のひとつだといえます。
インサイドセールスが役割を果たすためのKPI

インサイドセールスが適切に役割を果たすためには、公平で公正な評価を行うためのKPIの採用・設定が必要です。
バランスのよいKPI設定が必要
KPIとはKey Performance Indicatorの略で、重要業績評価指標と訳されます。最終的なゴールに向かう過程における目標の達成、進捗状況を評価する指標です。インサイドセールスは営業活動の量と質の両方が求められる職種であり、バランスが重要なためKPIもその前提で設定する必要があるといえます。
量的KPI
量的なKPIとは、数量で表すことができるKPIです。インサイドセールスにおける量的KPIには、架電数やアポイント獲得数、商談化数、受注数、受注金額などがあります。架電数やアポイント獲得数、商談化数などは営業の成果としての数字に至る前段階の量的KPIです。この数が多いほうが受注数の積み上げにつながり、受注金額の最大化にも貢献します。
しかし、架電数を追求すると短い通話に偏ってしまい肝心な話ができないなど、量を重視し過ぎると質がおろそかになり本末転倒になりかねません。この場合の架電はあくまでも手段であり目的ではないことを意識したKPIの設定が求められます。
質的KPI
質的なKPIは量的KPIの数を率に置きかえたものだといえます。つまり、アポイント獲得率や商談化率、受注率などです。たとえば、受注率が高くなれば受注件数も増えるはずです。
とはいえ、質を追求するあまり量が減ってしまいかねない点に注意する必要があります。2件中1件の受注なら受注率は50%です。しかし、もう1件商談を進めて3件中1件の受注に終われば受注率は33.3%に低下します。率の低下を防ぐために分母を抑えるという本末転倒の行動に走れば、結果的に受注数は増えません。仮に受注率が20%でも10件中なら2件の、20件中なら4件の受注となります。
KPIの量と質は単純な比較で決められるものではありませんが、インサイドセールスの役割のなかで初動にあたるフェーズでは、ある程度の量が求められるといえるでしょう。まずは間口を広げないことには、ナーチャリングすべきリードが集まりません。仕事が進むにつれて、質の向上が必要になります。
変化するインサイドセールスの役割

インサイドセールスの役割は常に一定というわけではなく、時間の経過とともに変化しています。営業プロセスにおける初動、リードナーチャリングをメインの役割とするだけでなくクロージング、受注まで担当するケースもあるのが現在のインサイドセールスです。その理由や原因を中心にみていきましょう。
オンラインでの商談が増えている
従来型の客先を訪問してクロージング、受注を行う営業活動がすべてではなく、オンラインで完結する商談が増えています。オンライン完結であれば対面である必然性がなく、訪問する必要もありません。そのため、インサイドセールスが受注まで担う事例が増えています。
オンライン完結の商談を後押しする背景として、新型コロナウイルス感染症拡大や、それを契機に広まったリモートワークの推進が考えられます。人が接触すれば感染リスクが高くなるため、営業活動の非対面化が進んだといえるでしょう。
サブスクリプション型のプロダクトが普及している
月額制や年額制の請求で定額サービスを提供するサブスクリプション型のプロダクトが普及している状況も、インサイドセールスの役割に受注活動が加わっている原因のひとつです。
サブスクリプション型サービスは内容が理解しやすく、必要性やプラン選択の判断がしやすいサービスが多いことからクロージングの比重が減っているといわれています。初期費用が無料のサービスが少なくない点も導入へのハードルを下げている要因です。このような事情から、問い合わせを受けたインサイドセールスの説明によって購入が決まるケースが多くなり、インサイドセールスが受注までまとめて担当するほうが効率的となっているのです。
ターゲットによって営業プロセスを変えている
リードの業種や企業規模などの条件により、営業プロセス、インサイドセールスの役割を変える企業が存在しています。たとえば、SDRのリードのように、顧客側からアクセスしてくるケースでは、購入意欲が高いケースが少なくないことから、初動対応を行うインサイドセールスがそのままクロージングを行います。一方、BDRのような大手の株式会社相手の営業活動では、ナーチャリングを進めてフィールドセールスに引き継ぐといった使い分けです。
インサイドセールス3つの型
インサイドセールスは役割の違いにより3つの型に分けることができます。一般に考えられている営業プロセスの一部、商談化までを担当する分業型、1人で営業活動のほぼ全部を担う単独型、先ほど述べたようなターゲットにより役割を変える混在型の3つです。ただし、インサイドセールスの役割に統一的な定義があるわけではないため、各社で同じ運用が行われているとは限りません。そこに明確な線引きはなく、細かい役割は企業によって異なる点に注意が必要です。
インサイドセールスのメリット
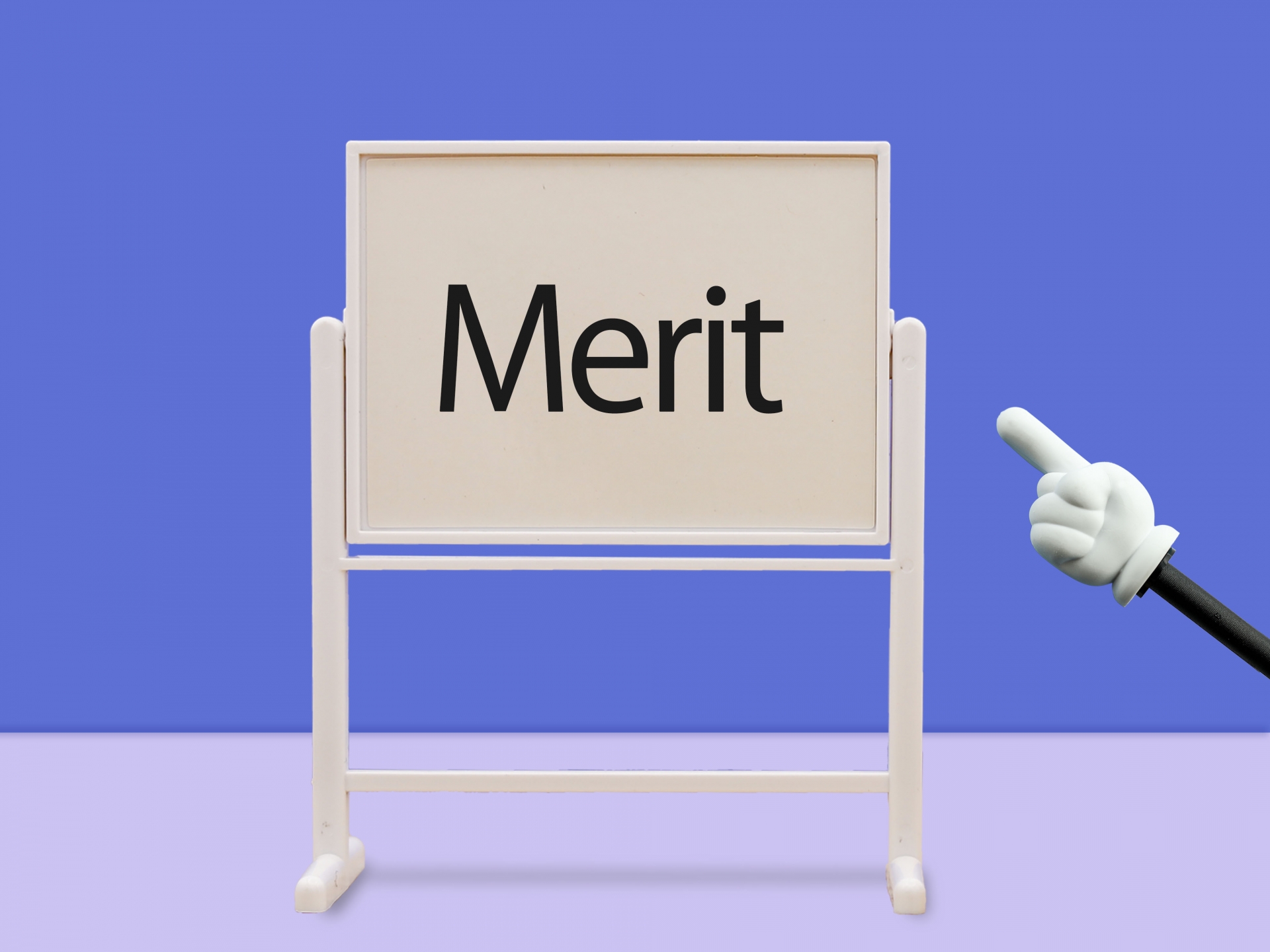
インサイドセールスを導入、運用する主なメリットを解説します。
営業効率のアップ
インサイドセールスの大きなメリットのひとつが営業効率のアップです。営業活動にあたって客先を訪問する必要がないため、移動で時間を費やすことがありません。同じ時間でも訪問営業に比べて多くの顧客を担当できます。また、初動対応からリードナーチャリングに集中できるため、より効果的な営業活動が可能です。さらに、リードの状況を容易に確認できるため、優先順位を考慮したアプローチや成約に近い案件に注力することができます。
営業エリアの拡大
電話やメールその他のコミュニケーションツールを活用して顧客にアプローチするインサイドセールスは、相手先の企業がどこにあったとしても、自分のデスクから動くことなく営業活動ができます。したがって、営業エリアの拡大が容易です。訪問型の営業スタイルの場合は、時間的・コスト的に営業エリアを絞る必要が生じ得ますが、移動時間も交通費もかからないインサイドセールスなら、その点からの制限がありません。
分業による機会損失の防止
インサイドセールスが初動対応とナーチャリングを担当し、フィールドセールスが訪問による商談を進めてクロージングを行う分業体制により、機会損失を防止できます。インサイドセールスを導入していない場合は、移動に時間を使うフィールドセールスの役割が多くなってしまい、限られた時間では手が回らず他社に遅れをとるケースが生じかねません。
営業コストのカット
初動対応やリードナーチャリングのための訪問を行わないインサイドセールスの導入によって、営業プロセスの途中までは交通費や移動時間の人件費がかからなくなります。とくに遠隔地の顧客対応を行う場合、かかる費用も時間も大幅に圧縮されるため、コストカットの効果は大きいといえるでしょう。
人的リソースの有効活用
すでに述べたメリットにも関連していますが、訪問しない営業活動を行うインサイドセールスは、少ない人数で多くの顧客を担当することができます。訪問営業をやめることで余裕ができた人的リソースを、他の重要な業務に充てることが可能です。
BCPで大きな役割を果たす
BCP(Business Continuity Plan = 事業継続計画)は、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症拡大とリモートワークの広がりで注目度が上がったといえます。インサイドセールスは、コミュニケーションツールやITツールの利用が可能なWeb・通信環境があれば、オフィスが使えない状況でも運用可能です。大規模災害や騒乱などに際し、事業の継続や早期再開を目指すBCPにおいて、インサイドセールスが果たす役割は大きいといえるでしょう。
インサイドセールスの課題
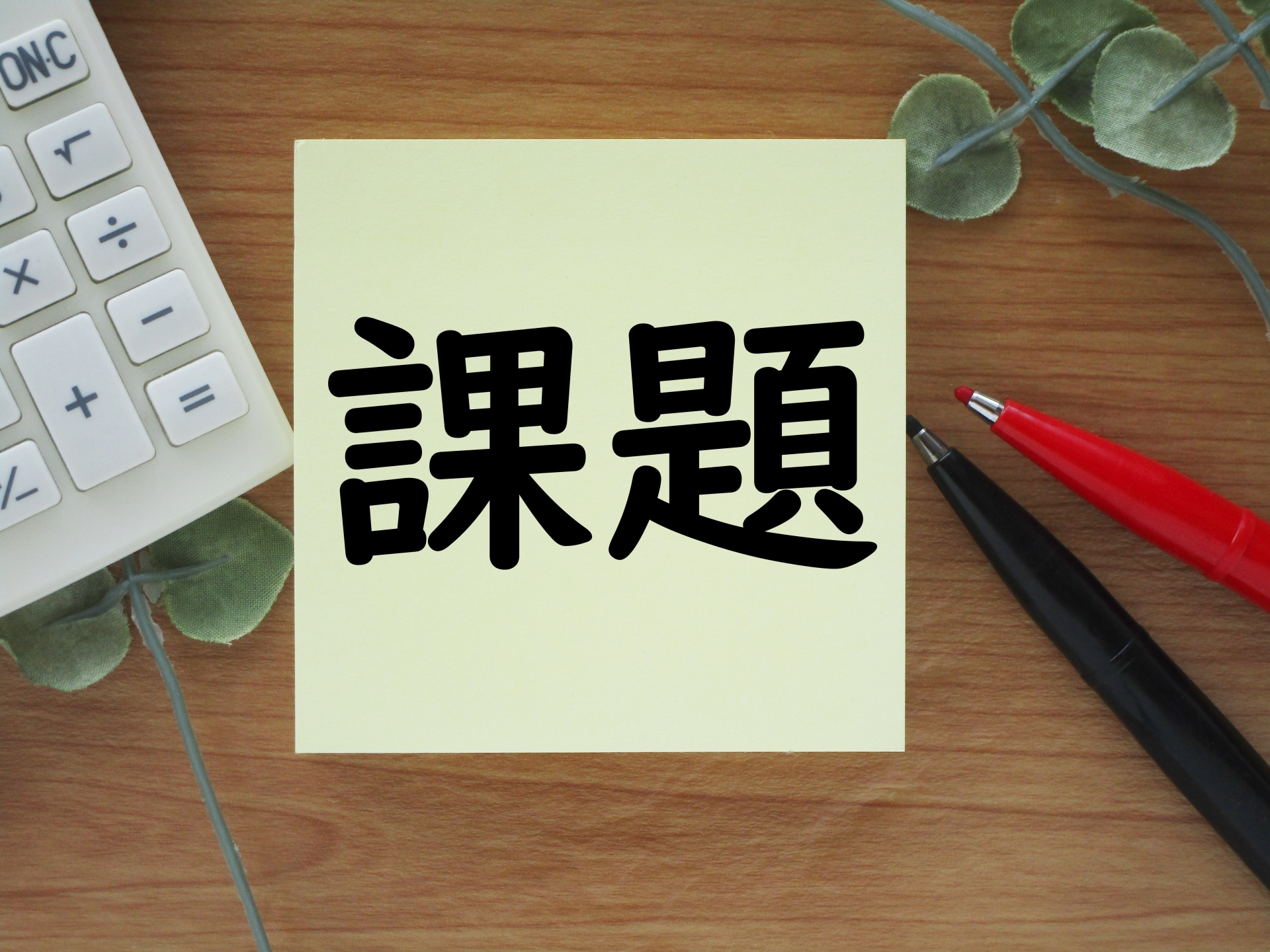
インサイドセールスの性質上、メリットと裏返しの課題がないわけではありません。主な課題と課題があるなかでも期待される将来性について解説します。
顧客との関係構築の難易度が高い
インサイドセールスのメリットである訪問しない営業活動は、生産性を上げる可能性が大きいと同時に顧客の顔を見ないで信頼関係を構築しなければならないことを意味しています。対面での営業よりも難易度が高い傾向がある点が課題、デメリットです。
IT技術を使ったコミュニケーションツールを活用することで、非対面での関係構築のハードルを下げることは可能ですが、しっかりとした準備とより丁寧なコミュニケーションが必要です。また、個人のスキルやチームとしてのノウハウの蓄積、教育なども求められるでしょう。
案件の引継ぎ率に注意
営業プロセスの分業化では、インサイドセールスがナーチャリングを実施したリード、案件をフィールドセールスに引き継いでクロージングにつなげます。このとき、案件の引継ぎ率に注意が必要です。引継ぎ率が低ければ、ナーチャリングがうまく行っていないことが考えられます。ナーチャリングが進まない原因の解明や改善が課題です。
引き継いだ案件の質にも注意
引継ぎ率が高かったとしても、成約につながらなければインサイドセールスの役割を果たせたかどうかがわかりません。引き継いだ案件の質が悪くて成約につながらないなら、インサイドセールスの判断が適切ではなかったことになります。リードの取捨選択やナーチャリングのやり方も含めて、インサイドセールスの課題です。
多様なニーズに応える時代のインサイドセールスは将来性あり
インサイドセールスの働き方はリモートワークとの親和性が高く、働き方改革が叫ばれる社会にマッチしているといえるでしょう。また、営業する側の企業は人材不足のなかで営業プロセスの効率化に向けた見直しを考え、顧客企業はオンライン環境の拡充でなるべくなら営業マンの訪問を受けないで、効率よくプロダクト選びを済ませたいニーズを持っています。インサイドセールスは多様なニーズに応える時代の営業の形であり、将来性にも期待できる職種です。
インサイドセールス導入成功のポイント

インサイドセールスの採用、導入を成功させるために徹底したい主なポイント、コツを解説します。
スモールスタート
インサイドセールスの導入にあたっては、スモールスタートがおすすめです。ノウハウも経験値もない状態で、いきなり大規模な取り組みを行うことはハードルが高いといえます。インサイドセールスは営業プロセスの一部を担うポジションであり、マーケティングやフィールドセールス、カスタマーサクセスなどとの連携が必要です。スモールスタートからはじめて徐々に規模を拡大することで、大勢のインサイドセールスが円滑な連携を実現できるようになるでしょう。
仕組み作り
インサイドセールスを導入する目的、担う役割を明確にし、分業する営業プロセスのどの部分までを責任範囲とするか決めておくことが重要です。他ポジションとの連携や運用ルールなど管理方法、人材配置といった組織整備に至るまで、しっかりとした仕組み作りを行います。この作業ができていないと、作業の抜けや重複、情報共有不足といった問題が生じかねません。
ITツールの活用
非対面で営業活動を行うインサイドセールスを効率よく運用するために、欠かせないポイントといえるのがITツールの活用です。インサイドセールスに役立つITツールにはCRM、SFA、MAなどがあります。
連携意識の強化
インサイドセールスの担当者はもちろんのこと、営業プロセスの一翼を担う各ポジションの担当者には、チームのメンバーとして連携意識の強化が求められます。属人化が珍しくなかった従来型の営業活動とは異なり、一匹狼的な営業マンはインサイドセールスに向いていません。
インサイドセールスの始め方
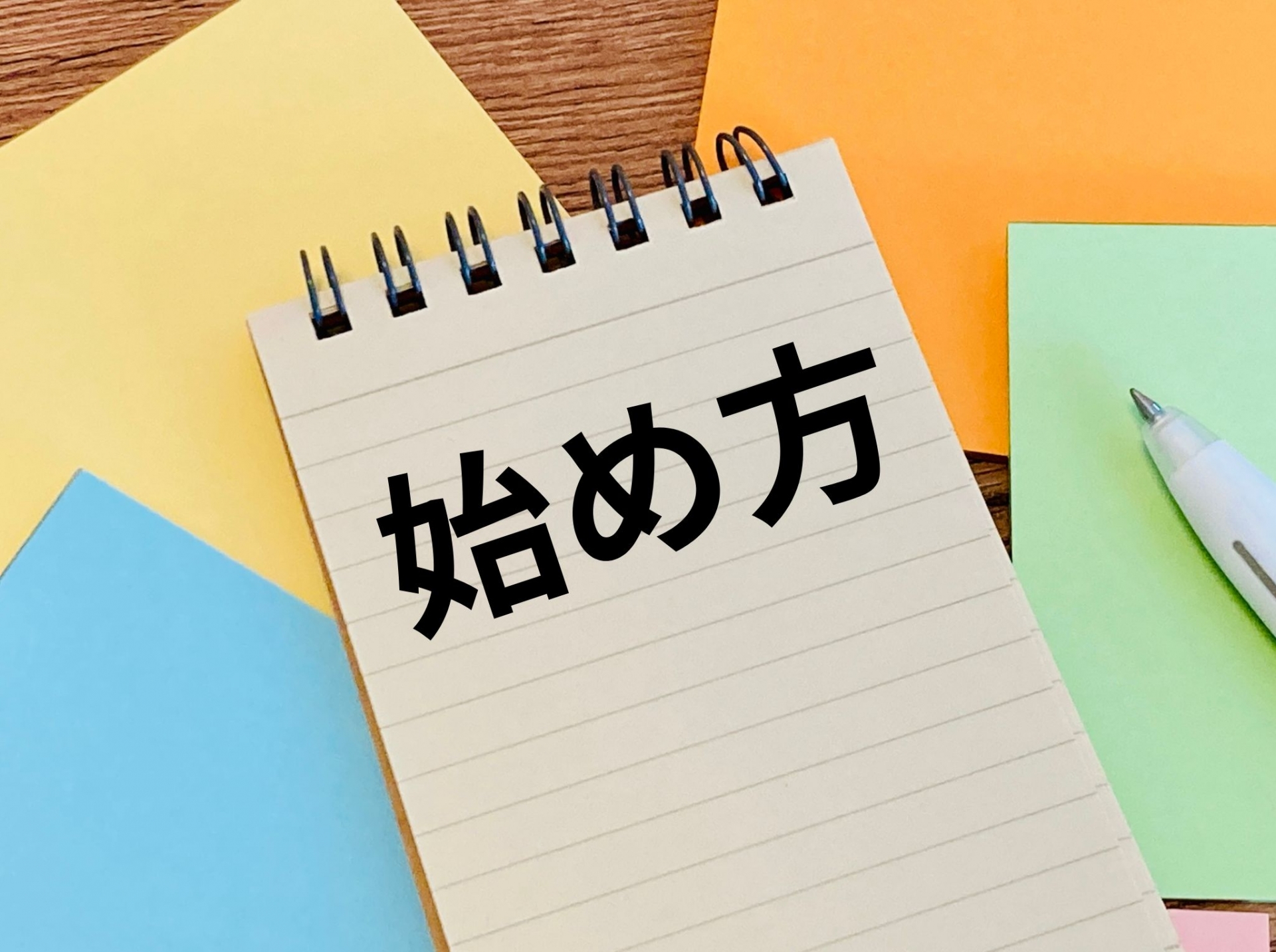
一部に前述の導入成功のポイントと重複する部分もありますが、インサイドセールスの導入を円滑に行うための始め方、手順を以下で解説します。
目的の明確化
インサイドセールスを導入する目的を明確にします。現状の問題点や課題の解決策として、またはより効率のよい営業活動の実現のため、求める役割と具体的な職務内容の決定が重要です。
人員・組織の整備
インサイドセールスを担当する人員を決定し、組織を整備します。インサイドセールスはマーケティングやフィールドセールスなどの営業チームメンバーと情報共有し、適切に連携して業務を進める必要があるポジションです。
ナーチャリング中のリードに関する情報の多くを最初に入手することになるインサイドセールスは、他部門に情報を提供したりサポートしたりする存在となります。そのため、自分の担当範囲だけでなく、営業プロセス全体を客観的な視点で見て連携をとれる人材の配置が必要です。
キャリアプラン策定
インサイドセールスの仕事は会社にとって重要な仕事であることは間違いありません。とはいえ、ずっとインサイドセールスを担当するだけでは物足りないと考える人材がいても不思議ではないでしょう。そこで必要になるのがキャリアプランの策定です。インサイドセールスからフィールドセールスへのキャリアチェンジ、経営戦略部門へのキャリアアップなど、キャリアプランを示すことは、配置した人材が先を見据えて積極的に職務にあたるために欠かせません。
KPIの設定
KPIの設定は前述したように、量的KPIと質的KPIのバランスを考慮して行います。量に偏るとナーチャリングが進まず、成果につながりにくい活動に時間をとられることになりかねません。このような弊害を避けるには、求める成果から逆算してKPIを設定する方法があります。
また、インサイドセールスはクロージングを行いませんが、受注率や受注件数といった売上・利益に直結するKPIを設定することで、フィールドセールスとの連携意識の強化が期待できるでしょう。
連携体制の整備
連携意識が強化されただけでは円滑な連携ができるとは限りません。連携体制の整備が重要です。インサイドセールスによってナーチャリング中のリードがどの段階にあるかを可視化して共有したり、どのような情報を積極的に共有すべきかをルール化したりします。また、フィールドセールスに引き継ぐタイミングについても、具体的な判断基準を設けておくことが重要です。
ITツールの導入
CRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援システム)、MA(マーケティングオートメーション)といったITツールには、人力作業の代行による業務の自動化や進捗管理、情報の共有や分析などインサイドセールスの活動を効率化する効果を期待できます。すでに導入している場合は、既存システムが業務にマッチしているかを検討する必要があるでしょう。未導入の場合は、お試しやデモの様子を参考にするなど、自社に必要な機能を考慮して選びます。
トークスクリプトの作成・トレーニング
実際にインサイドセールスとしての業務を行うことを想定し、シナリオやトークスクリプトの作成とトレーニングを行います。現実に即した内容であることが重要です。
運用とブラッシュアップ
インサイドセールスを運用することで生じる問題点や課題を見過ごすことなく拾い出して改善します。よりよいインサイドセールスとなるように、ブラッシュアップは欠かせません。
転職に向けて知っておきたいインサイドセールスの役割を果たすために必要なスキル

インサイドセールスへの転職を考えているなら知っておきたい、役割を果たすために必要なスキルを紹介します。
信頼関係構築に必要なコミュニケーション能力
インサイドセールスにはさまざまなスキルが必要ですが、まずはコミュニケーション能力が重要です。ほぼ関係性がないところからスタートするリードとの信頼関係を構築するためには、適切なコミュニケーションをとる必要があります。
課題把握に必要な情報収集力・ヒアリング力
信頼関係の構築と自社の商品・サービスが役立つか否かの判断を行うためには、リードが置かれている状況や抱えている課題を正確に把握する情報収集力とヒアリング力が必要です。
課題解決に必要な分析力・思考力・発想力
把握した課題の解決に向けた分析力や思考力、発想力も欠かせません。課題解決は自社の商品やサービスの活用が前提となるため、商品知識があることが前提となります。
ソリューション紹介に必要な提案力
自社の商品・サービスを中心としたソリューションの紹介は、顧客目線で納得できるものである必要があります。ただの売り込みになってしまわないように過不足のない説明を行い、ソリューションの導入意欲を強くさせる提案力が必要です。
積極的に活動する行動力
積極的に活動する行動力はインサイドセールスに限らず営業職には必須といえるスキルです。インサイドセールスの成果は、SDRであれBDRであれ、リードにアプローチしないことには発生しません。消極的な姿勢でリードが育つことは滅多にないなど、インサイドセールスは受け身では成り立たない仕事です。
めげないで職務にあたる忍耐力
インサイドセールスの仕事は必ずしも楽しいことばかりではありません。リードから軽くあしらわれたり、強いクレームを入れられたりすることもあります。そうした状況が続いたとしても、めげないで職務にあたる忍耐力が必要です。
インサイドセールスの将来性

インサイドセールスへの転職を考える際、気になるポイントのひとつが将来性です。働き方改革やDX推進社会、ITの進化に少子高齢化といった時代背景のなかでは、営業プロセスの分業化、専門分化が進むことはあっても後退することは考えにくいといえるでしょう。
インサイドセールスが担っている役割の重要性は変わらず、導入する企業が増えることが予測されます。関連する職種や上位キャリアへの転身も含めて、インサイドセールスは将来性ある職種のひとつです。
営業プロセスで重要な役割を果たすインサイドセールスは将来性もある仕事
インサイドセールスはリードに対する初動を受け持つ職種であり、確度の高い見込み客となるか否かを左右する重要な役割を担っています。営業プロセスの効率的な再編やコスト削減など、インサイドセールスを導入するメリットも多数です。実績を積んだうえでのキャリアアップなど、将来性もあるインサイドセールスの仕事は転職の選択肢として有望だといえるでしょう。
9Eキャリアインサイドセールスの転職支援サービスでは、インサイドセールス職を募集する企業の裏側まで熟知したエージェントが転職を支援いたします。
さらに、応募書類作成のサポートや企業ごとの面接対策など徹底した伴走型の転職支援を提供。「書類も面接もこれまでより通過率がダントツに上がった」「年収交渉をしてもらい希望年収が叶えられた」などクチコミでも高い評価をいただいています。カスタマーサクセス職での転職を成功させたい方はぜひ以下ボタンから面談予約してください。
この記事の監修者
小能見 理沙
大学卒業後、公務員としてキャリアをスタートするも、自身の成長のため独立。未経験から営業に挑戦し、3ヶ月で目標を大幅に達成する。この経験から「人生を変える一歩を支援したい」と決意し、キャリアアドバイザーに転身。
株式会社9E入社後は、半年で売上1位を記録しリーダーに昇格。現在はキャリアアドバイザーのスペシャリストとして、インサイドセールス職やカスタマーサクセス職への転職支援で年収大幅アップなど多数の実績を持つ。(▶︎詳しく見る)
インサイドセールス基礎知識のおすすめ記事
-
2025/06/04
インサイドセールスがうまくいかない理由とは? 5つの失敗事例をもとにポイントを解説
-
2024/12/09
インサイドセールスはやめとけ・辛いと言われる理由とは?向いている・向いていない人の特徴やキャリアも解説
-
2024/12/09
インサイドセールスとフィールドセールスの違いとは? それぞれの役割や分業のメリット・デメリット・ポイントを解説!
-
2024/12/09
インサイドセールスに向いてる人、不向きな人の特徴とは? 求められるスキルや適性も紹介